この記事でわかること
- 共有名義とはどういう状態か?
- 共有不動産によくあるトラブル事例
- 売却や管理で意思決定が難しくなる理由
- リスクを減らすための3つの現実的対策
- 専門家に相談するタイミングとメリット
相続や家族間でありがちな「共有名義」が実はトラブルのもと?
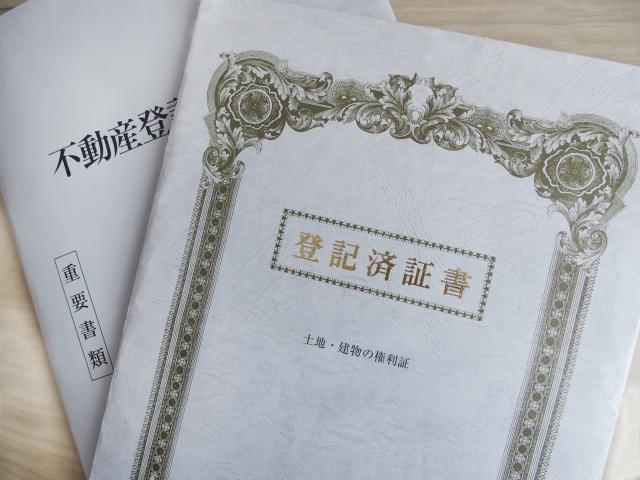
相続や資産管理の場面でよく見られる「共有名義の不動産」。
兄弟や親子で共同所有しているというケースは多いですが、実は後々トラブルに発展しやすい状態でもあります。
たとえば…
- 「売却したいけど、他の人が同意してくれない」
- 「一人だけが固定資産税や修繕費を負担している」
- 「連絡がつかない共有者がいて何も進まない」
というような問題が、年数が経つごとに複雑化していくのが実情です。
「共有名義」ってどういう状態?
共有名義とは、1つの不動産に複数人が所有権を持っている状態のこと。
たとえば
- 相続で兄弟3人に均等に相続された
- 親と子で住宅ローンを組んだ際に名義を分けた
などがよくあるケースです。
一見、平等に分けられたように見えますが、実際には「全員の同意がなければ何も動かせない」という制約があります。
共有名義で起きがちなトラブルとは?
売却や賃貸の合意が取れない
1人でも「反対」と言えば売ることができず、空き家のまま維持費だけがかかることに。
税金や管理の負担が不公平に
「住んでいる人だけが負担している」「一人が修繕費を出している」といった不満が蓄積し、家族関係にも影響します。
連絡が取れない共有者がいる
引っ越しや疎遠により、意見を聞くことすら難しくなると、売却や手続きはほぼ不可能に。
相続を重ねて「共有者が増える」
共有者が亡くなると、その権利がさらに分散。将来的には10人以上の共有者になるケースもあります。
リスクを減らすための3つの方法
1.持ち分をまとめる(買い取り・贈与・遺言など)
可能であれば、話し合いにより誰か1人にまとめるのが理想です。
- 共有者同士で持ち分を売買する
- 贈与によって名義を集約する
- 生前に遺言書で名義の整理を決めておく
といった方法が有効です。
2.相続前の工夫で「分散」を防ぐ
まだ相続が発生していないなら、「最初から共有名義にしない」工夫が有効です。
- 長男に不動産を相続
- 他の相続人には現金や金融資産を分ける
- 生前贈与で分け方を整理しておく
というように、分け方のバランスと納得感を両立させる設計が重要です。
3.家族会議と専門家のサポートを
今は問題がなくても、共有者の生活や考え方は数年で変わります。
「いざ」という時にスムーズに動けるよう、
- 一度家族で現状を話し合っておく
- 信頼できる専門家に方向性を相談しておく
という準備が、将来のもめごとを防ぎます。
よくあるご質問
- 兄弟との共有名義になっている実家、将来どうしたらいいか不安です。
- 放置すると複雑化するので、今のうちに整理方針を話し合いましょう。分筆や持ち分売買も視野に入れられます。
- まだ揉めていないのに相談してもいいですか?
- もちろんです。「今は大丈夫」なうちにご相談いただくのがベストタイミングです。
- 法的な手続きや分筆も対応してもらえますか?
- 必要に応じて、提携する司法書士・税理士などと連携して対応可能です。
無料相談で不安を解消しましょう
共有名義の不動産は、年数が経つほど解決が難しくなります。
今のうちに整理しておきたい
将来、家族間で揉めないように備えておきたい
株式会社ホームリアライズ(住宅のマイスター日進・名東店)では日々、このようなご相談を、専門家がお受けしています。
不動産相続に関わることならぜひ弊社にご相談ください。

 日進・名東店
日進・名東店